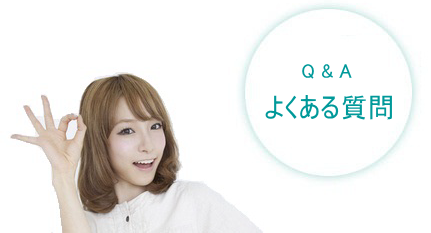 concept
concept
Q&Aの使い方

Q&Aはなるべく簡易にわかりやすく作成しておりますが少し細かい知識や単語を要するので「STEP1〜STEP3」をお読み頂く中で疑問に感じたこと、わかりずらかったことが出てきた時にそれらを補うようにお使い頂ければよろしいでしょう。
Q&A
A.破産とは,自分の収入や財産で支払わなければならない借金等(債務)を支払うことができなくなった場合に,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
財産とは,不動産,自動車,現金,預金,他人への貸金,保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金),将来受け取ることのできる退職金等すべてのものを含みます。
Q2.破産申立ては,弁護士や司法書士に頼まなくても,自分でできますか。
A.破産申立ては,あなた自身でも手続を行うことができます。
Q3.弁護士や司法書士に依頼した場合,どれくらいの費用がかかりますか。
A.裁判所に納める費用とは別に,依頼するための費用がかかります。費用については,依頼しようとする弁護士又は司法書士にお尋ねください。弁護士や司法書士に依頼した場合に支払う費用等と,自分で申立てをする場合にしなければならない作業等の負担とを,きちんと比較して選択してください。
なお,裁判所が弁護士や司法書士を紹介することはありません。また,自己破産の申立てをしようとしている人に近づき,資格がないにもかかわらず申立書等を作成して,その報酬を要求する者がいるという情報がありますので十分に注意してください。
Q4.弁護士に依頼すると,弁護士は何をしてくれますか。
A.弁護士はあなたの代理人として,裁判所へ呼び出された時に同席してくれたり,裁判所へ提出すべき書面の作成をしてくれたりします。そのほかに,弁護士に依頼すると,以下のような利点があると言われています。
弁護士が受任通知(依頼を受けたことを通知する書面)を発送することによって,取立行為(電話による催促や自宅等への集金)が中止される。
債権者への書類の発送,取立て等への対応を弁護士が行ってくれることにより,自分が直接債権者と対応することがなくなる。
Q5.司法書士に依頼すると,司法書士は何をしてくれますか。
A.司法書士は,弁護士のようにあなたの代理人として破産手続を行うことはできませんが,裁判所に提出すべき申立書等の書面や債権者へ発送する書面(例えば,破産申立ての通知書等)の作成を行ってくれます。
Q6.弁護士又は司法書士に依頼しないで自分で手続をする場合は,どうすればいいのですか。
A.自分で破産手続開始・免責許可申立書の作成やこれに関連する書類の作成及び提出をしなければなりません。自分で破産手続開始・免責許可申立てをする方のために破産手続開始・免責許可申立書を裁判所に用意していますので,必要な方は,裁判所の受付窓口に行き,書き方等手続の説明を受けてください。なお,ここをクリックして申立書の書式をダウンロードできます。
また,裁判所は,債権者と債務者の双方に公平・中立でなければいけませんので,破産手続開始・免責許可申立てに関する手続の一般的な説明はできますが,債務をどのような方法で整理するのがよいのか,破産手続開始の申立てをした方がよいのかといった個別の相談に応じることはできませんし,また債権者からの取立行為に対する対処等についてのアドバイスをすることもできませんので,これらの相談は,弁護士又は司法書士にお願いします。
Q7.最近は,「破産宣告」という言葉は使わないのですか。
A.そうです。破産法が改正され,「破産宣告」という言葉自体はなくなり,「破産手続開始決定」(裁判所が,破産手続の開始を宣言する決定を出すこと)という言葉に変わりましたが,意味は同じです。
Q8.どこの裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをしたらいいのですか。
A.原則として,債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。住民票上の住所と現住所が異なる場合には,現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
このほか,既に,自己破産の申立てをしている方と,(1)お互いに連帯債務者となっている方,(2)お互いに保証人となっている方,(3)夫婦である方については,同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。
Q9.「同時廃止」という言葉をよく耳にしますが,どういう意味ですか。
A.通常,裁判所は,破産手続開始決定を行うと同時に,破産管財人を選任し,この管財人が破産者のすべての財産を調査・管理し,これをお金に換えて債権者に分配することになります。
しかし,破産者の財産が少なく,これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。これを破産の「同時廃止」といい,この場合には,債務者の財産を管理したり,お金に換える手続は行われません。破産手続は終わり,免責手続に入ります。
Q10.破産管財人が選任される破産手続とは,どのような手続なのですか。
A.破産管財人が選任される破産手続とは,破産管財人が,破産者の持っている全財産を換価・処分・回収し,集めたお金を債権を届け出た債権者に配る手続です。破産者が破産に至った経緯,破産者の財産状況及び今後の見通しなどについては,債権者集会(債権者集会が行われる際は,その都度,裁判所から開催のご案内をさせていただきます。)において,破産管財人から説明を受けることができます。破産者の全財産を換価・処分・回収しても,債権者に配るべきお金がない場合には,破産手続を終了させることになります。
Q11.破産管財人とは,どういうことをする人なのですか?
A.裁判所が破産手続開始決定と同時に選任する,破産者の財産を管理する人です。管財業務は,法律関係の処理が必要であることから,法律の専門家である弁護士が選任されることがほとんどです。破産管財人は,(1)破産財団(※1)の占有・管理,(2)破産原因と破産財団の調査,(3)破産債権(※2)の調査,(4)破産財団の換価,(5)別除権(※3)・取戻権・財団債権(※4)への対応,(6)契約関係の処理,(7)訴訟関係の処理,(8)否認権(※5)の行使,(9)経理関係の処理と税金の報告,(10)債権者集会での報告等の業務を行います。
※1 破産財団…
債務者が倒産し,破産手続開始決定がされた場合に,破産者のすべての財産が破産者の管理下から離れ,破産者から独立した破産管財人の管理に置かれた状態にある財産のこと。
※2 破産債権…
破産手続によって,破産者の財産から支払等を受ける債権のこと。破産管財人が,債権額等に応じて配当等をします。
※3 別 除 権…
破産財団に属する特定の財産から,他の債権に先立って支払等を受けることのできる権利のこと(例 抵当権,根抵当権等)。
※4 財団債権…
破産手続によらずに,破産債権者(※2の債権をもっている者)に優先して,いつでも破産財団から支払等を受けることができる破産法上の債権のこと。例えば,税金や裁判に要したお金など。
※5 否 認 権…
破産手続開始決定前に破産者がした行為の効力を否定して,失われた財産を破産財団に回復する破産管財人の権利のこと。
Q12.破産手続開始・免責許可の申立手続費用は,いくらくらいかかりますか。
A.(1)同時廃止事件の場合(原則として)
官報(※)公告掲載費用 現金10,290円
破産手続開始・免責許可申立手続費用 収入印紙1,500円
書類の送付費用等 1,000円切手 1枚
80円切手×債権者数+5枚
40円切手 1枚
(2) 管財人選任事件の場合
同時廃止事件の場合より費用がかかります。詳細は,担当係にお問い合わせください。
※ 官報…政府が一般国民に知らせる事項を編集し,毎日刊行する公告文書
Q13.手続費用は,いつまでに納めたらいいのですか。
A.申立てのときに納めていただきます。
Q14.破産手続開始・免責許可申立ての際に,必要な資料は何ですか。
A.住民票,預貯金通帳の写し等です。
Q15.申立ての際に,注意することは何かありますか。
A.裁判所へ提出する書類は,A4判のサイズでコピーしてください。書類送付用の封筒(長形3号)を債権者の数分用意し,それぞれに債権者の宛名を記入してください。
Q16.破産手続開始の申立てをすると,年金が打ち切られることはないですか。
A.年金を打ち切られることはありません。国民年金や厚生年金等の年金受給権は,法律上,差押禁止財産となっていて,破産手続開始決定により影響を受けません。
Q17.破産手続開始・免責許可の申立てをしたことは,裁判所から債権者に知らせてもらえるのですか。
A.裁判所から債権者に破産手続開始申立てがあった旨の通知は行っていません。破産手続開始申立書を受け付けた際に,破産手続開始申立てについての「受理票」を交付しますので,申立人において,その写しを債権者に送付してください。
Q18.破産手続開始の申立てをしたことが勤務先に判明することがありますか。
A.破産手続開始決定がされると,裁判所は決定がされたことを債権者に通知する必要があるので,判明している債権者には,裁判所から書面で決定がされたことを通知します。したがって,勤務先からの借入れがある場合等には,会社にも通知が行くことになります。会社に対して債務がない場合は,裁判所から勤務先に破産手続開始がされたことを通知することはありません。
Q19.破産手続が開始されると,何か制限を受けるのですか?
A.管財人選任事件の場合
(1)財産に対する管理処分権限の喪失
破産手続開始決定以後は,破産管財人が財産の管理処分を行うことになります。
(2)居住移転の制限
裁判所の許可がなければ,その居住地を離れることができません。
(3)郵便物の受信制限
破産者に宛てた郵便物は,破産管財人に転送されます。
(4)公私法上の資格制限
弁護士,公認会計士,税理士,司法書士,後見人,保険外交員,警備員,株式
会社や有限会社の取締役等にはなれません。
なお,免責許可決定が確定すると,公私法上の資格制限は消滅します。仮に,
免責が許可されなかった場合でも,破産手続開始決定を受けてから10年を経過した時点で消滅します(これを「復権」といいます。)。また,選挙権や被選挙権等の公民権が喪失することはありません。
同時廃止事件の場合
上記(4)の公私法上の資格制限を受けます。
Q20.破産手続が開始されたら,住民票や戸籍に記載されるのですか。
A.記載されません。
Q21.破産手続が開始されたら,家族にも不利益がありますか。
A.破産することによって発生する利益や不利益は,破産者だけが受けるのであり,破産者と親族関係にあるということだけでは,その人たちには何らの影響はありません。保証人になっていない限り,支払義務はありません。また,親族の進学,就職,結婚等にも影響はありません。親からの財産の相続権がなくなることもありません。
Q22.免責とは何ですか。
A.破産手続で債権者へ支払われなかった債務について,支払義務を免除することです。破産手続開始決定を受け,破産手続が終了しただけでは負債の支払義務は免除されません。その後の審理の結果,免責許可決定がされ,その決定が確定すると,破産者が破産手続開始決定前に負担した債務は,税金や罰金等の一部の例外を除いて支払う責任がなくなります。また,破産手続開始決定によって喪失した法律上の資格等を回復(復権)します。
Q23.免責許可の申立てをしても免責許可決定を受けることができない場合があるのですか。
A.免責許可の申立てがされた場合,裁判所は,事情を調べた上で,免責許可決定をするかどうかを判断することになりますが,破産者に一定の事由があるときは,免責許可決定をすることができません。例えば,次のような場合には,免責を許可することができないとされています(もっとも,このような場合でも,裁判所の裁量により免責が許可されることがあります。)。
・債権者に害を与える目的で,自分の財産を隠したり,その価値を減少させた場合
・破産手続の開始を遅らせる目的で,高利の業者から借入れをしたり,クレジットカードで買物をしてその品物をすぐに安い値段で業者に売り払ったり質入れしたりした場合
・特定の債権者に対し,特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で,義務がないのに,特定の債権者に対する債務に担保権を設定したり,返済したりした場合
・浪費やギャンブル等にたくさんのお金を使って,借金を増やしたような場合
・破産者が破産手続開始申立ての1年前の日から破産手続開始決定の日までの間に,本当は支払ができない状態であるのに,そのような状態でないと信用させるため,嘘をつくなどして,相手を信用させ,お金を借りたり,商品を購入したりしたことがある場合
・破産者が嘘の債権者名簿を提出し,または財産状態について嘘を述べたり記載したりした場合
・破産者が前回の免責許可決定確定日から7年以内に免責許可の申立てをした場合
・破産者が破産法の定める破産者の義務に違反した場合
例えば,裁判所の許可なく居住地を離れたり,逃走したり,嘘の意見を裁判
所に申し出て,不当に手続を進めたりした場合です。
Q25.免責許可決定が確定すると,あらゆる債務の支払の責任が免除されるのですか。
A.免責許可決定が確定し,その効力が発生しても,あらゆる債務の支払の責任が免除されるわけではありません。免責の対象となる債務は,破産手続開始決定時の債務に限ります。ただし,税金や罰金,過料,悪意をもって加えた不法行為による損害賠償請求権,故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権,夫婦間の婚姻費用分担請求権,子に関する養育費請求権,従業員等の給料請求権,破産者が債権者一覧表に記載しなかった債権等は破産法上非免責債権とされ,免責の効力が及びません。つまり,それらは支払わなければなりません。
免責されない債務及び請求権の一覧
自己破産で免責許可決定が下りても以下の債務および請求権は免責されません。
法令は「破産法の第253条(免責許可の決定の効力等)」を参照ください。
・税金、罰金等
・悪意をもって不法行為を行ったことで発生する損害賠償請求権
・故意又は重大な過失により人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・夫婦間の扶助の義務、夫婦間の共有財産、離婚後の子供の養育費、三親等以内の扶養義務に基づく請求権
・破産者が会社や事業など経営している場合の、労働者の給与や源泉税・社会保険などの預かり金
・債権者名簿に任意に記載しなかった請求権で、債務者の破産手続きがあったことを相手が知らない場合
A.免責の効力は,破産者以外には及びません。したがって,保証人又は連帯債務者がいる場合,その保証人又は連帯債務者は,破産者の免責許可決定確定後も,依然として支払義務を負います。
Q26.免責許可決定が確定したら,裁判所から破産者に通知が届くのですか。
A.裁判所は,免責許可決定の通知はしますが,その後の確定した旨の通知はしません。免責許可決定が確定したことを書面化したいのでしたら,免責許可決定確定証明申請をしていただくことになります。免責許可決定確定証明申請には,収入印紙150円が必要になります。
offece info.事務所案内
濱岡司法書士事務所
破産相談コーナー
〒547-0044
大阪市平野区平野本町5-14-20
日野上ビル4階
TEL.06-6796-1406
FAX.06-6796-1407
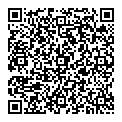
>>アクセス
簡単スリーステップ
無理なく借金を返済する方法
よくある質問 Q&A
ちょっとひといきBreakTime
増えてるの?自己破産?
どこから借りているの?
買うか?賃貸か?
自己破産今後のゆくえ
教育資金の問題
税金・国民健康保険・年金・公共料金等の問題
住宅・医療・その他の問題
ダウンロード
過払金をチェックする

